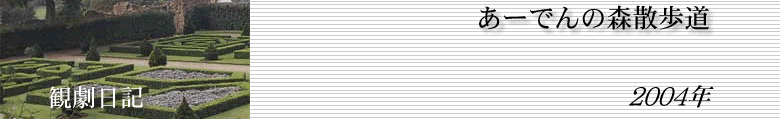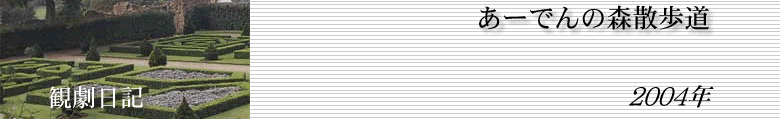〜 シンボライズされた舞台と沸騰する演技のエネルギー 〜
沸騰するようなエネルギーが噴出する激烈な演技が舞台を走る。
蜷川幸雄の『タイタス・アンドロニカス』は、結局のところ、この劇のすべての出来事とその意味を、エンデイングに集約してしまう。
舞台大詰めの、ラヴィニア、タモーラ、タイタス、サターナイナスの残虐な惨劇のことではない。 原作にはない、小ルーシアスが叫ぶ悲憤のエンデイングである。
これらの悲劇的な惨劇が終わり、タイタスの息子ルーシアスがローマの皇帝に推挙され、感謝の言葉ともろもろの事後処置について演説したところで、シェイクスピアのドラマは終る。が、蜷川幸雄の舞台は、さらに続く。
ルーシアスが演説を終えてバルコニーから立ち去った後、舞台に残ったローマの兵士達と護民官達、そしてルーシアスに従ってきたゴートの兵士達も次々と舞台から退場していく。
最後に残ったエアロンの赤ん坊を抱いたゴート族の兵士が、ルーシアスの息子、小ルーシアスにその赤ん坊を託す。
小ルーシアスは、舞台下手の端から中央まで、その赤ん坊を抱いてゆっくりと歩いてくる。
小ルーシアスは、赤ん坊を抱いたまま、両膝を落として床に膝まずく。そして天を仰ぐようにして、「あああ・・・・あっ」と悲嘆の叫び声を発する。ゆっくりと、しかしながら、力強く、その叫びは五度繰り返される。
腕に抱かれたエアロンの黒い赤ん坊が象徴的である。
小ルーシアスの悲痛の叫びは、無限大の解釈の可能性があるが、直訳的な解釈を許さない厳しさがある。
赤ん坊との関連性で解釈すれば、「我々は泣きながらこの世にやってきた」「生れ落ちると泣くのはな、この阿呆の桧舞台に引き出されたのが悲しいからだ」というリアの台詞も思い出される。
戦争の犠牲や、親のエゴの犠牲とも解釈される。
だが、この演出の凄さは、どのような解釈も許さないような小ルーシアスの叫びである。
それは、そこに至るまでのドラマ(=演技)をすべて集約して、無化させてしまう力をもっている。
『タイタス・アンドロニカス』は、シェイクスピアの作品の中でも最も初期の悲劇で、その残虐性において他の作品と異にする。
シェイクスピアの時代の娯楽の一つに、処刑の見物があった。当時の処刑では、四つ裂きの刑や、生きながらにして内臓を抉り出し、それを口に咥えさせるような残虐な処刑があった。そういう見物を楽しむ観客にとっては、タイタスが、タモーラの二人の息子の生首でパイを作ることなど、ぞくぞくする面白さであったかも知れない。
シェイクスピアとは異なる時代性にいる現代の観客にとっては、タイタスの世界はグロテスクで異様な世界と写るかもしれない。
蜷川幸雄の演出では、その異様なグロテスクさを浄化するかのように、舞台装置は「白」で統一されている。
ローマの元老院の建物や、平和時のローマ貴族の服装は、白色である。そして、バシエナイスの殺害や、ラヴィニアの陵辱がなされる森もまた、白で統一される。大樹と蓮の葉の形状をした植物の色も白一色である。
おびただしく流される血は、赤い細い紐の束で表象され、カリカチュア化されることで、その残虐性が希釈され、グロテスクさが希薄化される。
舞台は、このように装置と衣装がシンボライズされている。
そのシンボルの中心軸は、ローマ建国のシンボル、「カピトリーノの雌狼」像である。
この像も、真っ白な塑像である。大きさは、象の実物大を想像するといい。その大きさの像が、場面によってその位置を変えることで、舞台表象する。
タイタスがサターナイナスを愚弄した手紙を持参した道化の登場の場面では、唯一、この像が観客席に尻を向けた位置に置かれる。サタイアとユーモアを感じさせる演出である。
台詞力で圧倒する吉田鋼太郎が剛直なタイタスを熱演し、存在感を出している。
それを受けて立つ麻美れいのタモーラも、冷酷な気品と気性で、妖艶な色香の凄みを感じさせる。
岡本健一のエアロンも、この劇の内面的な深みに欠かせない好演であった。
エアロンの存在は、『タイタス・アンドロニカス』のドラマを、単なる残酷でグロテスクな興味本位の見世 物芝居から、人間性の普遍性へと高めている。そこには、『オセロ』のイアーゴの原型が見られるだけでなく、このドラマの、悲劇の影の主軸ともなっていることで特徴がある。岡本健一は、ニヒルにそれを演じきっている。
途中15分の休憩時間を挟んで、3時間15分の上演時間が、走るようにして過ぎ去った。
「カピトリーノの雌狼」像の台座に横たわって死んでいるタモーラの姿が印象的であった。
それらもすべて、冒頭で述べたように、小ルーシアスの叫び声一つに集約された。
訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄、装置/中越司
1月18日(日)14時開演、彩の国さいたま芸術劇場・大ホール
チケット:(S席)9000円、座席:1階F列21番
|