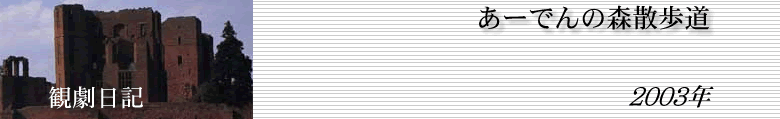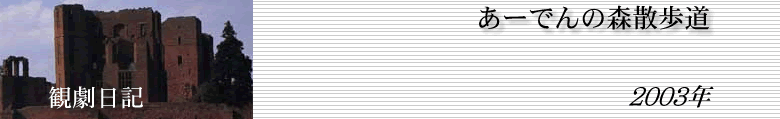1999年2月、彩の国さいたま芸術劇場公演の再演であるが、今回初演とはかなりキャステイングが変わっている。初演を観ていないので比較はできないが、当時の紙上評判で、開幕冒頭のすさまじいばかりの天井からの落下物のことは知っていたので、そのこと自体への驚きや衝撃はなかった。
キャステイングについては、主演の市村正親のリチャード、嵯川哲朗のバッキンガム、菅生隆之のヘイステイングズ卿は変わっていない。助演級で初演と異なるのは女優陣で、エリザベスの有馬稲子が夏木マリに、アンが久世星佳から香寿たつき、マーガレットが楠侑子から松下砂稚子、ヨーク公爵夫人が中村美代子から東恵美子となっている。
初演時との演出の違いが出ているかどうかは知らないが、当時と今日との大きな状況の差は、9・11テロとイラク戦争問題であろう。今回の演出で感じられたのは、その戦争やテロの影である。蜷川幸雄の演出は、大きな想像力・創造力の割には、テキストに忠実である。テキストを踏み外した解釈での演出はないが、テキストの範囲内でメッセージを強く伝えている。今回はエンデイングにおいて強いメッセージを感じる。
暴君リチャードを倒し、白バラと紅バラの統合を宣言するリッチモンドの声は、演説の途中から宇崎竜童のダイナミックなカオスの音楽にかき消されていき、冒頭の場面と同様に、舞台に栗毛の馬が走ってきて駆け巡り、ドウと倒れる。そして、天井からは激しく落下物が落ちてくる。開幕時よりももっと凄まじく、激しい。このエンデイングは象徴的である。
開幕冒頭では、白馬が舞台を駆け巡り、そして倒れ伏す。そこへ天井から落下物が落ちてくる。その間、舞台中央奥には、赤い布切れが風になびいているのが見えるのが印象的である。落下がやみ、あたりが落ち着いたところで、その赤い布切れが動き出す。それはリチャードのマントだったのがそこで初めて分かる。
市村正親のリチャードは、目には隈取がされており、姿かたちは傴僂(せむし)でびっこを引いている。
今年は演劇集団円公演の『リチャード三世』で、金田明夫のリチャード、文学座公演では江守徹のリチャードを観ており、三者三様のリチャードに特徴が出ている。
金田明夫のリチャードが一番陽気で、道化的要素を感じた。高さの違う靴を履くことで、多少びっこを引く程度で、異様さを強調する姿かたちもしておらず、衣装でそのアクセントを出している程度であった。
江守徹のリチャードは、圧倒的な存在感を示しながらも、憎めないだけでなく、好感を感じさせた。
それに対して、市村正親のリチャードは、シェイクスピアの本から出てきたようなリチャードである。異様さを強調したリチャードである。
初演時と比較して、今回は「台詞にこだわる」というのが演出家、蜷川のポリシーであったそうである。そのことは劇を見終わった後で「プログラム」を読んでから知ったのであるが、観ていて非常にオーソドックスな流れだという印象が強かった原因がそれで分かったような気がした。反面、原文を読んでいるだけに、何か物足りなさも感じた。翻訳の限界ともいうべきものだろう。台詞劇としてのシェイクスピアだったら、どうしても原文の韻律の調子には適(かな)わない。しかし、圧倒的な存在感で迫るリチャードの市村正親に対して、夏木マリのエリザベスの台詞や所作は、強い存在感を感じさせた。
メタリックな格子構造の舞台装置、場面ごとにそれが鏡の壁面にも入れ替わる。
場面ごとに宇崎竜童の音楽が入り、スピード感と躍動感のある舞台で、休憩20分を含む3時間の上演時間が短く感じた。
(訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄、12月20日夜、日生劇場にて観劇)
|