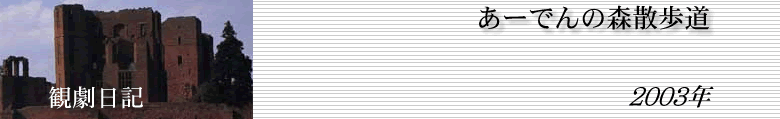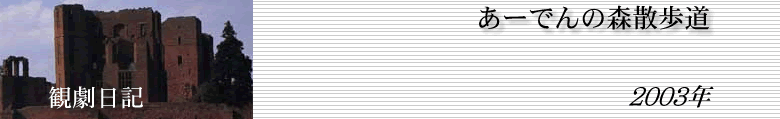舞台は横幅を広く取って、中央に4本、小型版の風力発電のプロペラが横並びに並んでいる。そのプロペラが登場人物の感情の起伏やドラマの展開に伴って、時には2本、時には4本全部が羽を回転させる。その回転方向も、感情の動きやドラマの展開につれて右回りをしたりしたり、逆回転したり、それを繰り返したりすることで、場面の静的な動きに起伏を与えるシンボリックな役割を果たす。
頭上には、紗織の布が雲を抽象画にしたイメージで天蓋のように吊るされている。この紗織の天蓋も、照明で色調を変えるや、吊り紐で高さが上下させることで、舞台の展開の変化を示す。
レオンテイーズ、ハーマイオニ、貴族たちによるボヘミア王ポリクシニーズのもてなし、鳥に扮した無言のパーフオマンスの後、ポリクシニーズの帰国を引きとめようとして、物語は展開される。
鳥に扮した衣装と、鳥のイメージが全体の重要なモチーフとなっている。衣装は、水分を含むとそこだけが色が変わり、汚れたようになる。過ち、堕落、罪などの表象となる。そして鳥そのものは、「時」のシンボルとして表象される。
シェイクスピアの後期ロマンス劇が、死と再生が重要なテーマとなっているのはよく知られるところである。
「鳥」は鶴のように見えるが、死と再生のシンボルとしてみれば、フェニックスとして解釈できる。それを具象化するのは、レオンテイーズの息子マミリアス。「鳥」の頭部の被り物を手にもてあそびながら一人遊びをするのだが、最後の大円団である再会の場面、ハーマイオニの再生の場面でも、死者として部外者ながら他者との交流のない存在で登場し、鳥の独り遊びに没頭している。
ガリンスキーの演出で際立った特徴は、シチリア王国の場面とボヘミア王国の羊飼いの場面が、一般的に見られる演出の「暗」と「明」の落差が殆どないことだろう。レオンテイーズの嫉妬と、その神罰が下る前半のシチリア王国でのドラマは「激」であり、「暗」である。そして「時」をはさんで後半の、ボヘミア王国の羊飼いの場面は、「活」であり「明」である。その前半と後半の対比が著しいだけに、最後の再会と再生とが感動的なドラマになる。その落差がない、ということは悪く言えば、全体が平板となった印象を感じた。クライマックスの昂揚感に欠けた気がした。ハーマイオニの再生の感動が強く感じられなかったのはそのためであろう。この場面では感動の昂揚で泪が出るのだが、今回はそこまでならなかったのが残念であった。
羊飼いの場面での明朗感と躍動感の欠如は、毛刈り祭りでオートリカスの物売りの場面が大きくカットされていることにあったと思う。このオートリカス登場の場面は、後半盛り上げにかなり重要な役割をしていると思うが、それを楽しませてくれる不足感の不満を感じた。
羊飼いがパーデイタの出自を証明する品を、実際にレオンテイーズに差し出す演出は、今一歩で感動的となるところをストップ・モーションで暗転してしまい、折角の昂揚感が抑えられフラストレーションを感じた。冗長さと蛇足感を抑えた演出としては、その方がベターかも知れないのだが。
レオンテイーズを演じる中野誠也、羊飼いの立花一男、ハーマイオニの川口敦子など、俳優座を代表するメンバーが出演しているが、持ち味の発揮となると、アンサンブルとしては物足りなさが残った。
(松岡和子新訳、W.ガリンスキー演出、11月27日夜、俳優座劇場にて観劇)
|