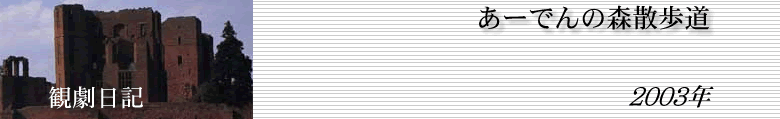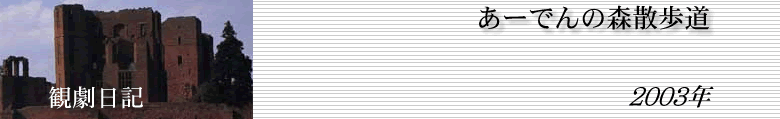坪内逍遥訳 × 江守徹主演 × レオン・ルービン演出=文学座公演 『リチャード三世』
今回の文学座の『リチャード三世』公演は、上の公式で前宣伝があったので、「やっとヨークの朝彦の天下となったので、我党の陰鬱な冬が去り、陽気な、快活な夏が来た」のような坪内逍遥訳がどのような台詞回しで語られるのかという興味と期待が最初にあった。これはまったく予想を裏切る形で、思い切り現代風の台詞となっていた。あえて坪内逍遥訳としたのはどういう意図からであろうか。
次に大きな特徴としては、マーガレットの登場がないということと、ショア夫人に関連した台詞が省略されている。そして舞台の時代設定と背景が現代に近い中国風であるということ。それは舞台衣装と銅鑼や鉦の音から生じる印象である。衣装について言えば、平和な世の中では出番のないリチャードは、瞑想と国王戴冠式の場面とを除けば終始軍服姿である。そのことがリチャードを独裁者としての存在を意識させるのに効果的でもあったように思う。
江守徹のリチャードは、足が多少不自由で、左肩が持ち上がった傴僂姿で身体的には異形であるが、特別に異形さを強調した容貌とは感じなかった。それは悪役でありながら狂言回しをも務めるコミカルな台詞回しからくる印象のせいだろう。江守徹のエネルギーとパワーにあらためて感心させられる演技でもあった。
レオン・ルービンのオリナリテイではないが、舞台にニュース報道として映像の場面を活用していたのも今回の特徴でもあり、事件進行の同時性を感じさせる現代的感覚の演出法であった。その中でも印象的なのは、ヘイステイングズ卿処刑のニュースを流すニュース・キャスター(原作では公証人)が、本番前にその処刑について真相の本音を語った後、本番では何事もなかったように淡々としてそのニュースを読み上げる場面である。
また、バッキンガム公と市長や市民達が、リチャードに国王就任の嘆願に来る瞑想の場面では実況中継として映像が映し出され、現実の舞台と映像が同時進行する。
戦況の報道を映し出す映像は現在的であり、イラク戦争やテロ事件を連想させるのに十分である。映像の中で報道者は都市の路地から実況し、その背後で都市が攻撃されビルが崩壊する。日常性と非日常性の同時存在。
ボズワースの戦場での亡霊の場も、映像の活用と実際に亡霊を舞台に登場させることで、その効果を昂揚させていた。
舞台全体を通しての印象は、江守徹のリチャードの圧倒的な存在感。リチャードを演じるには、相当のエネルギーとパワーを求められるということが、江守徹の演技を通して感じられる。
『リチャード三世』がシェイクスピアの作品の中でも人気がありながら上演される機会が少ない理由の一つはそこにあるのだろう。
映像での印象しかないが、ローレンス・オリヴィエのリチャードは、冷たいニヒルな悪人で、あまり好きになれない気がするが、イアン・マッケランの現代版リチャードは、どこか憎めないものをもっていた。江守徹のリチャードも、憎めないだけでなく、好感をも感じさせる。もちろん実際にそんな人物が自分の傍にいたら耐えられないと思うが、虚構の世界では、許せる存在、愛しうる人物として演じられていたと思う。
(世田谷パブリックシアターにて、11月1日夜、観劇)
|