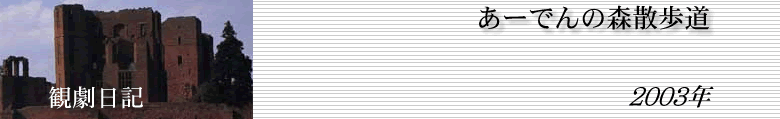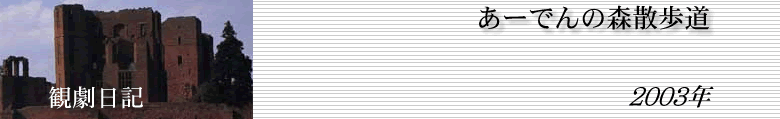シェイクスピアの『じゃじゃ馬ならし』は、荘子の「胡蝶の夢」を思わせるものがある。
― 夢の中の胡蝶が私なのか、胡蝶が夢の中で私という人間になったのか、夢が現実なのか、現実が夢なのか・・・・・。
居酒屋の前で酔いつぶれて寝込んでしまった鋳掛け屋のクリストファー・スライを、領主とその従僕たちが屋敷に連れ帰って領主に仕立て上げる。目覚めたスライは、すっかり領主になった気分にさせられる。そこへやって来た役者の一行によりスライのために喜劇が供せられる。『じゃじゃ馬ならし』はその劇中劇の形態をとっている。
シェイクスピアはこの世を舞台に見立てていて、それは初期の喜劇から、歴史劇、悲劇、そして後期のロマンス劇を通して一貫して見られる世界観、人生観である。『じゃじゃ馬ならし』はシェイクスピアの作品の中でも比較的初期の喜劇とみなされている。そのせいというわけでもないだろうが、『じゃじゃ馬ならし』はこの、夢=現実=舞台という関係が、未分化の状態にある作品といえる。
なるほど、スライは目覚めて領主にされ、そして劇を観ることになる。しかしこの劇中劇はスライを現実に引き戻すことなく、劇中劇のまま終ってしまう。スライにとって鋳掛け屋が本来の自分であったのか、それとも領主となっている今の自分が現実なのか、夢なのか、劇を観ているのも夢なのか、渾然としたまま劇は終ってしまう。
マイケル・トウイードウル演出の独創的な面白さの一つに、このスライの夢=現実の渾然とした未分化の状態を、劇中劇においてスライをペトルーチオとして登場させたところにある。芝居が始まって間を置かず、退屈さの余り居眠りを始めてしまったスライが、いきなりペトルーチオとなり、領主としてのスライの妻に扮装していた小姓がペトルーチオの召使グルーミオとなって舞台に登場し、劇中劇をともに演じ始める。
このことによって、鋳掛け屋スライの現実、夢から覚めた領主、劇中劇のペトルーチオという関係で、現実=夢=舞台という等式が成り立ってくる。
演出のマイケルは、舞台設定の時代と場所を1920年代のオックスフォードに置き換えることによって、ホーテンショーやルーセンショーらの由緒正しい貴族階級と、物欲的な新興成金階級のグレミオや、アメリカナイズされたライフスタイルのペトルーチオといったカリカチュア化された人物像を造形する。そしてペトルーチオの召使グルーミオは、台詞よりも身振りで笑わせるサイレント映画の喜劇人物チャーリー・チャップリンのそれである。
1920年代のオックスフォードの設定という概念が、結果的にオックスフォード大学演劇協会という自らの出自を模倣するということで、この世は舞台という二重構造を成していて面白かった。
(世田谷・シアタートラムにて、7月30日夜観劇)
|