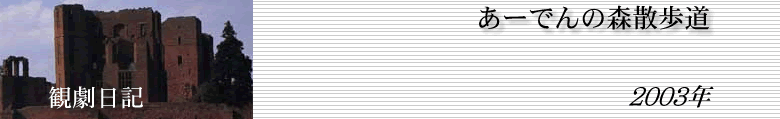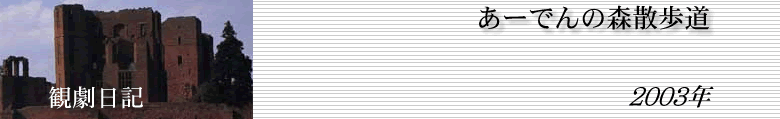開演とともに、幕の内側からメタリックなロックの音楽の喧騒と叫喚。そして幕が開くと、舞台下手で踊りに興じる若者達と、上手奥の高台に立ってそれを眺め見下ろしているエドワード四世とエリザベス王妃。
舞台下手後方からリチャードが踊りに興じていた連中の拍手を得ながら登場。テレビなどでもおなじみのせいか、観客席からもリチャード役の金田明夫に拍手がわく。凸型の張り出し舞台まで出てきて、王や踊っていた連中に手を振って挨拶し、張り出し舞台の床に置いてあったマイクをとりあげ、演説を始める。そう、それはリチャードの独白というより、演説といった方がいい。エドワード王を称えるようにして、
「さあ、俺たちの不満の冬は終わった、栄光の夏を呼んだ太陽はヨークの長男エドワード」
と賛美する。ここからまず、我々は陽気なリチャードの印象を抱かされる。
そのリチャードの容姿は不自然な異形を避け、足の不自由さは、片方の靴を厚底の靴にして、足の長さのバランスを崩してびっこを引いて歩かせる程度のもので、傴僂の背中も、手足の不自由さも、リチャードの黒の衣装に、不自由な側の手先や足先、そして肩のほうに、黄褐色をしたギザギザのフリルのような布切れで表象するのみである。その衣装のありようが、リチャードの道化的要素を印象付けるという効果をもっている。
上演時間は途中15分の休憩時間を挟んで2時間20分。原作のカットによる短縮効果だけでなく、つなぎのテンポがよく、軽快なスピード感が現代的な感覚を募らせる。
演出は、円での演出が初めて、というだけでなく、シェイクスピアの演出も初めてという、平光琢也。入団後10年で一度円を退団した後、「お笑い」の道に進み、ミュージカル「セーラームーン」の脚本・演出など商業演劇の演出にも活躍している。主演の金田明夫とは円演劇研究所に一緒に入団し、一緒に退団し、また一緒に出戻りした、という切っても切れない仲である。
今回の上演で非常に強く感じさせられたことがある。ヨーク公爵夫人のリチャードに接する態度とその言葉を聞いていると、リチャードは母親の愛を生まれながらにして得られなかっただけでなく、疎まれ、呪われた、悲しい哀れな存在であったということである。ヨーク公爵夫人を演じる高林由紀子の持つ気品と穏やかな表情から出てくる台詞だけに、一層冷酷な印象が深まる。そのような不幸な生まれのリチャードに思わず同情したくなってくる。母の愛を知らずして育った子が、どんな大人になるか。
リッチモンドに敗れたリチャードは、舞台奥の、梯子を横向きに倒したような装置の上に背中を舞台正面に向けて横向きに倒れ伏した状態で死ぬ。そのリチャードのところへ、静かな足取りでヨーク公爵夫人が近づき、膝を屈してリチャードの頭をそっと撫でるかのような所作をする。その余韻を残して舞台は暗転し、幕が下りる。
公爵夫人の台詞に、「どうして不幸は口数が多いのだろう」というのがあるが、リチャードが死んだ今初めて、饒舌が消え、沈黙が支配し、不幸は飛び去ったと公爵夫人は思ったであろうか。リチャードは死んで初めて母親の愛情を得ることができたでろうか。そういうことを感じさせる余韻である。
<舞台メモ、その印象と感想>
冒頭のリチャードの独白(この演出では先にも書いたように演説調)シーンの台詞は、軽快であるだけでなく、最後の方では歌う節回しで語られ、聞いていてのりのよい心地よさの印象を残す。
リチャードの兄クラレンスの逮捕と入れ替わりにヘイステイングズ卿がロンドン塔から釈放される場面で、ショア夫人がヘイステイングズと一緒に登場する。ショア夫人は台詞こそないが、もう一度登場する。スタンリー卿からの使い(この使者の設定を、スタンリー卿の息子ジョージとしているのも斬新な演出だと思う)が来た時、寝室からヘイステイングズは出てくるが、その寝室にはショア夫人がいる。ショア夫人の登場はオリヴィエの『リチャード三世』でもあるので、特に目新しい演出ではないが、注目に値する演出だった。
王妃エリザベスの連れ子であるドーセット侯爵を演じる佐藤せつじが、いかにも成り上り者で、教養と品性に欠ける若者を演じて、そのいやみさをうまく表わしているのが目についた。
マーガレットは、舞台下手の観客席通路から、風呂敷包みを抱え、杖をついて登場する。その風呂敷包みには一個の髑髏がはいっており、マーガレットはその髑髏を頭上に掲げて呪いの言葉を吐く。さんざん呪いの言葉を吐いた後、舞台を降りて上手の観客席通路から劇場出入り口より退場する。
このマーガレットのイメージが、シェイクスピアの原作で感じる印象と、演じる片岡静香とのギャップを感じてならなかった。そのギャップがなんに由来するのか表現しにくいのだが、安っぽいというか、薄っぺらいというか、凄みに乏しい感じである。
アンとエドワード・リチャード両王子の殺害場面が、同時進行形で舞台上に演出される。アンはラトクリフに絞殺され、舞台中央に倒れ伏す。一方王子たちは、舞台下手にセットされた寝室で、羽根が飛び散る枕で息を塞がれて殺される。その飛び散る羽根が象徴的である。
第1幕はここで終わって休憩。
第2幕は、王子達の殺人者テイレルが走り出てきて、二人の王子を殺したことを激しく後悔するところから始められる。
リッチモンドは女優の入江純が演じている。貴公子然とした印象をうまく出していたと思う。
リチャードの最後の台詞、「馬を!」というのを、傷つき倒れた後も、一人舞台に残って舞台下手、上手へと動いて、そのたびにスポットライトが当てられ、「馬を」、「馬を」とそのたびに繰り返す。それは、母の愛を追い求める悲しい叫びの表象であるかのように、今となっては感じる。
これまでの円らしからぬシェイクスピア劇の斬新さと、新鮮味を感じた。
(訳/松岡和子、演出/平光琢也、美術/加藤ちか、7月12日(土)紀伊国屋ホールにて観劇)
|