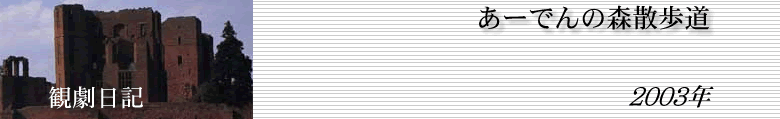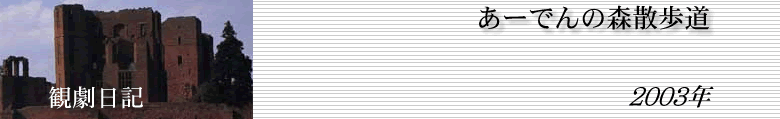〜 和洋折衷の異化作用が紡ぎ出す壮大なロマンス劇 〜
この劇を、荒唐無稽の夢物語、ということをこの蜷川幸雄の『ペリクリーズ』を観た後では、決して言えないはずである。かつて海路で産褥の妻を失い、その妻の忘れ形見と言うべき一人娘に14年後にやっとめぐり会えると思ったら、その娘も養育を託したターサスの太守の地で亡くしてしまって、今や絶望の淵に臥して廃人同様の状態にあるペリクリーズ(内野聖陽)が、死んだはずの実の娘マリーナ(田中裕子)の打ち明け話を聞くうちに、それがまさしく自分の娘であることが明らかになっていく時、そのペリクリーズの驚愕にも似た喜びと感嘆に、観ていてどよめきのような感動が込み上げてきて、嗚咽の感情が抑え切れずに、涙がどうしようもなく溢れ出してきたのだった。それほど現実的に胸に迫ってきたのだった。
蜷川幸雄の劇は、舞台装置からして衝撃的である。舞台装置は、蜷川幸雄の舞台では常連の中越司、照明が原田保、衣装が小峰リリー。音響は井上正弘。演劇は総合芸術である、ということを実践的に見せつけてくれる。舞台空間には、高さのさまざまな水道管とその蛇口が、水の受け皿としての大きなバケツとセットになって、舞台全体に林立している。その数は10ほどある。舞台全体を暗転させたとき、その水道管と蛇口とバケツだけがスポットライトを浴びて浮かび上がる時、森閑とした沈黙の饒舌を感じる。
戦争の銃撃戦のような音。舞台の上では、天井から、逆行するサーチライトの光のように、無数の照明が梁のように暗闇の舞台を交錯して走る。開演となって、観客席の通路から登場する俳優達は、あるものは傷痍軍人のように、あるものは敗残兵のように、あるものは戦争ですべてを失った市民のように、戦争で廃墟と化した町に戻ってきたようにして、三々五々舞台上に集まってくる。水を飲むもの、水を浴びるもの、その時、水道の水は、まさしく命の水となる。水の周りは、一瞬のオアシスを感じさせる。そして、蠢き徘徊する彼らが舞台前面の横一列に並んでお辞儀をする時、この劇が彼らによってこれから演じられるのだということが意味されていることを知る。
すべての物語が終わった後、また同じように、空には爆撃機の音、背後からは銃撃戦の音が聞こえ、これまで『ペリクリーズ』を演じてきた俳優達が、再び、戦場の傷ついた兵士や疲弊した一般市民の姿に変わって登場し、舞台を徘徊する。そして始まりと同様に、やがて彼ら一同が横一列に並んでお辞儀をして、「芝居」の芝居が終わったことを表現する。下手をすれば蛇足的な趣向だが、この物語の円環性を象徴する趣向でもある。これは『ペリクリーズ』というロマンス劇の円環性ではなく、むしろ戦争という寓意の円環性を感じさせる。01年の9・11テロ事件以来、すべての意味が一変したが、戦争は変わらないという円環構造。しかし、この劇で表出された戦争は、民族紛争のボスニア戦争をより多く感じさせたが、今進行形で近づいているアメリカによるイラクの攻撃のことを予兆せざるを得ない。
この劇の最大の特色は、口上役の詩人ガワーを、市村正親と白石加代子の二人に演じさせたところにある。蜷川幸雄は当初、市村正親一人に考えていたのだが、白石加代子が面白そうなので自分もやってみたいと言ったところから、ガワーを固有名詞でなく普通名詞としてとらえて、二人語りとしたということである。これは制作の過程での思わぬアイデアが生まれたいい例であろう。市村が演じるガワーは琵琶法師の様態で、びわの弾き語りで語る。また、ガワーが語る情景描写では、大きな鏡面を仕立てて能の鏡板を模し、人間が人形となって黒子に操られる文楽の形態で、物語の粗筋を表現するという趣向が凝らされる。これは物語の異化作用の効果を生み出している。西洋的物語と純日本的な様式の異質な組み合わせが、不思議なほどに違和感を感じさせない。
タイトルロールの内野聖陽以外は、登場する俳優全員が一人数役をこなす。その内野聖陽は、すべての希望を失って、虚脱状態で廃人のようになったペリクリーズを演じて娘マリーナを抱き上げる時、その再会の歓喜の姿顔形は、そのままでリア王を演じられると思った。というよりリア王その人を感じた。口上役ガワーを務める市村正親は、ガワー以外には、ターサスの太守クリーオン、ペンタポリスの王サイモニデイーズ、それにミテイリーニの太守ライシマカスの四役を演じ、白石加代子は、クリーオンの妻ダイオナイザー、それにミテイリーニの女郎屋のおかみを演じ、時に早変わりを強いられる。その演じ分けも見ものである。
ペンタポリスの騎士達の踊りは歌舞伎の様式になぞらえられるだろうし、田中裕子が演じるペンタポリスの王の娘、タイーサの踊りは、能を思わせる静かな様式的な踊りのようである。洋と和からなる異化効果がここにも現れているような気がする。田中裕子はタイーサとその娘マリーナの二役をこなす。
観客席の最後列から舞台中央のペリクリーズに向かって、エフェソスへとペリクリーズを誘いざなうダイアナは、後光の射す観音像のようにも見える。そしてペリクリーズがダイアナの夢のお告げで出向いたエフェソスのダイアナの神殿は、能舞台の鏡板そのままに、神木として松の木が大きく描き出されており、西洋の神殿というより日本の神社を思わせる。小峰リリーが紡ぎ出す衣装も、異国風の和様である。
音楽で強い印象を与えるのは、朴根鐘(パククンジョン)のチョッテ(横笛)の、哀調を帯びた鋭い音。ペリクリーズの内面の劇的な変調を表象するのに際立って効果的である。蜷川幸雄は音楽についても意外性を用いるが、今度のこのチョッテの音にはまた一つ驚かされた。韓国の民族音楽ではよく聞かれる音だが、シェイクスピアの場面でこのような形態で聞かされると、またその異化作用の効果が重層される。
蜷川幸雄の『ペリクリーズ』の感想を一口で表現すれば、圧倒するダイナミックさ、ともいうべきものであろう。感動のどよめきも一通りでなく、見る側に大きなエネルギーを消耗させる。感動の満足感を超えて、虚脱状態で劇場の外へと足を運ぶことになる。ロンドンでの公演の反響がまた楽しみである。シェイクスピアの台詞の言葉を超えた演劇の力をそこに感じることができるだろう。
(作/W・シェイクスピア、翻訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄、3月2日、
彩の国さいたま芸術劇場にて観劇)
|