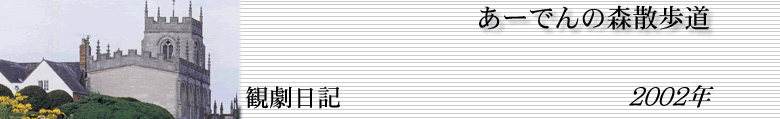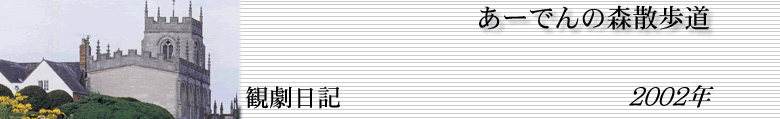〜紀伊國屋演劇賞受賞 吉田鋼太郎 ハムレット再演〜
昨年2月、高円寺のニュー・プレイスで上演されたシェイクスピア・シアターの『ハムレット』で、主演の吉田鋼太郎が紀伊國屋演劇賞を受賞したのは記憶に新しいところである。
ちょうど一年ぶりに、舞台を東京グローブ座に移しての再演である。
昨年の舞台では、最初と最後にローレンス・オリヴィエの映画『ハムレット』を使ってのなかなか興味深い演出であったが、今回は全くのストレートで変化球なしの演出である。小田島雄志の翻訳を直球に投げて、それを受ける俳優の肉体を通して、台詞劇の醍醐味をしっかりと聞かせてくれる舞台である。従って、舞台には全く何もない。最小限の道具は、クローデイアスとガートルードが座る2脚の椅子のみ。途中10分間の休憩をはさんでの3時間を、小気味よいテンポで上演する。
出口典雄の演出は、余分な解釈を挟まない。台詞こそが真実である。揺れるハムレットの言葉は、それそのものが真実。シェイクスピアの多様性、多義性をそのままの「素」の姿で演出するので、観る側の解釈に自由度の幅がある。
例えば。ハムレットが「尼寺の場」でオフイーリアを「愛した」という台詞も真実なら、「愛してなどいなかった」という言葉も真実。あるいはどちらも「虚偽」という真実。それはハムレットの揺れる相矛盾する感情の葛藤、心のカオス。そのカオスが渦巻く台詞となって迸る。観客はそのカオスをカオスのまま全体で受け入れる方が良い。
身体全体が台詞となって演技する吉田鋼太郎のハムレットは、昨年の日記にも書いたが、激しいマグマの噴流である。グローブ座の舞台を小さく感じさせるほどの、大きな演技力である。
『ハムレット』が単純な復讐劇でないことは確かであるが、吉田鋼太郎のハムレットを観て感じたことは、ハムレットの憂鬱は、父ハムレット王の死が原因ではなく、母と叔父の結婚に対する嫌悪感によるものである、ということ。亡霊の登場から、父の死がクローデイアスの手によるものと分かって、ハムレットは復讐の決意はするがなかなか実行はしない。その機会もなくはなかったのに、自分で理由を付けて決行しない。ハムレットがクローデイアスを殺すのは、母ガートルードが過って毒薬の入った酒を飲んで死んだ時である。その時のクローデイアス殺害は、父の復讐心からではない。母の死からくる、とっさの行為である。結局ハムレットは復讐をしえ得なかった。母の死がなければ、クローデイアスを殺すことはしなかった。復讐は偶然の結果でしかない。
前回も高く評価したホレイショーの杉本政志が一段とよくなったと思う。彼には大いに期待しており、楽しみな存在である。同じく、役者(座長)とフォーテインブラスを演じる田村真も、レアテイーズの平澤智之も、今後がますます楽しみである。
再演とは言え、演出も変化があり、充実した舞台で、気分新たに感動した。
(訳/小田島雄志、演出/出口典雄、東京グローブ座にて、2月10日(日)観劇)
|