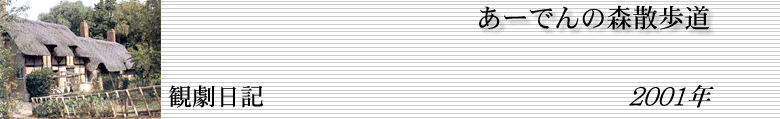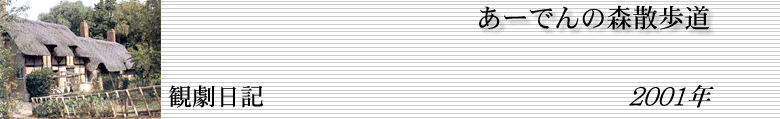存在の根元への問いかけ、「そこにいるのは誰だ?」
ピーター・ブルックの「ハムレットの悲劇」は、ホレイーショーの「そこにいるのは誰だ?」で始まり、ホレイショーの同じ台詞で終わる。ホレイショー以外は誰もいなくなってしまう。みんな死んでしまった。ホレイショーは、今まで夢を見ていたのであろうか?今、目の前で起こっていたことは、すべて夢の中の出来事だったのだろうか?ホレイショーの最後の台詞、「そこにいるのは誰だ?」の繰り返しは、この劇が終わりなく続くことを象徴する。ホレイショーは目撃者であり、証言者でもあることを体現するするかのような舞台演出である。
舞台は、<何もない空間>。
平土間に、朱色に近い真紅のカーペット。登場する入口もなければ、扉もない。登場人物は、舞台奥の両脇から、もしくは舞台正面、観客席の両脇の通路から登場する。
忽然とただ一人登場したホレイショーは、あたりを不安げに見回す。舞台は一瞬の間、真空状態となる。そして、ホレイショーは、その沈黙の重さに問いかける。
「そこにいるのは誰だ?」
<不安>は得体が知れないときに極限に達する。不安は亡霊の出現で、<恐怖>に変貌し、真空状態の均衡が崩れる。
時間にして数分にも満たないこの瞬間、観客は息を呑む音さへ聞こえるような静寂の中で、舞台に釘付けとなる。この瞬間に、もう舞台に電撃的にしびれてしまった。すべての感激がこの場から始まった。
「ハムレット」の登場人物は、台詞のある人物だけで30人いる。省略なしで上演しようとすると、現在ではまず4時間はかかるであろう。その「ハムレット」を、ピーター・ブルックは8人の俳優で、2時間半で上演する。そこで当然のことながら、ハムレットの<悲劇>に必要でない部分は大胆にカットされる。フォーテインブラスは、ハムレットの悲劇には何も関与しない挿話だということで、全く登場もしないし、話題にもならない。
2時間半の凝縮には必要なカットだけでなく、場面と台詞の順序の入れ替えもある。その入れ替えは、特にハムレットの独白において効果的になされる。
ハムレットの第1独白、「ああ、堅い堅いこの体、いっそ溶けて崩れ、露になってしまえばいい」も、ホレイショーが亡霊と出会った場面の直後、一人登場したハムレットの台詞として発せられる。この第1独白は、テクストではクローデイアス国王一同が退場した後になされるのだが、その順序も入れ替わっている。
最も有名な第4独白、3幕1場の「生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ」の台詞は、本来の場面ではなされない。この独白は、ハムレットが英国に送り出される4幕4場の場面(第7独白の場面)でなされる。父ポローニアスを殺されたオフイーリアが、舞台奥を下手から上手へと、今旅立たんとするハムレットの方を寂しげな眼で見つめながら通り過ぎる。そのオフイーリアの姿に触発されたかのように、ハムレットは'To be, or not to be'と独白する。
登場人物を8人で演じることについては、ハムレット、ホレイショー、ガートルード、オフイーリアスの4人は、役の兼任がない。亡霊役はクローデイアスを演じ、ポローニアスは墓堀人とオズリックを兼ね、ギルデンスターンとローゼンクランツの二人を演じる役が一番忙しく、役者1,2(劇中劇の王と王妃)、レアテイーズ、神父、そして貴族(ハムレットとレアテイーズの剣の試合の審判役)を演じる。
この劇を「ハムレット」ではなく「ハムレットの悲劇」としているのは、本来の悲劇性を強調してのことである。
最後、ホレイショーが「そこにいるのは誰だ?」と問いかけるとき、それはアイデンテイテイへの問いかけでもあり、自分の存在を確かめるためのものでもある。みんないなくなってしまった後、ここにいる自分は本当に存在しているかという根元的な問いの響きを持つ。もんないなくなってしまった、みんな死んでしまったということを強調するために、オフイーリアがみんな死んでいる場所にやってきて、そこで一緒になって死ぬことで表象している。
ピーター・ブルックの「ハムレットの悲劇」で忘れてはならないのは、音の魔術師、土取利行が紡ぎ出す演劇空間のすばらしさである。
ブルックが<何もない空間>から劇的空間を作り出す演出の魔術師だとすれば、土取は、その劇的空間を<真空状態>に昇華する音の魔術師であろう。
「ハムレットの悲劇」の台詞は、土取利行の紡ぎ出す音によって<息>を与えられる。役者の呼吸が台詞と同化しているように、土取の音楽は台詞の<キュー>の役割を果たしながらも自然と台詞に同化していく。 土取利行の音は、舞台の緊張感のテンションを高める。
感激度:★★★★★ <感激度寸評>新世紀の「ハムレット」誕生。クオート版でもなく、フォリオ版でもない、ピーター・ブルック版「ハムレットの悲劇」という新しいテキスト誕生。
(6月24日、世田谷パブリックシアターにて観劇)「あーでんの森散歩道」より再録、一部修正
|