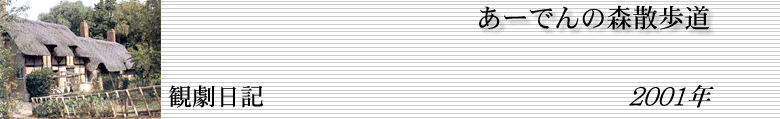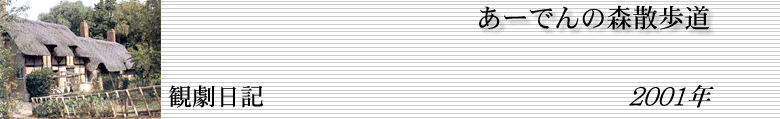ハムレット劇あれこれ
今年は21世紀初頭を飾るにふさわしい「ハムレット」劇の意欲的な演出が目立ったような気がする。
その第一弾が劇団四季の下村尊則と石丸幹二による異なる個性の二人のハムレット競演。劇団四季としても82年の劇団創立30周年記念公演(日下武史がハムレット)以来の「ハムレット」である。僕の観劇日記からその印象を拾い出してみると、
「まず特筆したいのが舞台美術。舞台装置と衣裳は、ジョン・ベリーとエリザベス・ベリー夫妻。ジョン・ベリーが創り出した舞台は、シンプルながら多様に変貌する。競技場のトラックを思わせる白線のラインが走る奥行きのある黒い舞台は、八百板(傾斜)舞台…下村尊則のハムレットは、中性的な<静>のハムレットである」
とあり、その印象は今も変わらない。そして、浅利慶太の演出については、よく調理されているが、カオスのダイナミズムがなく、まとまりすぎた仕上がりに物足りなさを感じた。
次が出口典雄のシェイクスピア・シアターによる「ハムレット」。この演出も印象的だった。冒頭、ローレンス・オリヴィエの映画「ハムレット」が映写され、地獄の亡者達がその映画をじっと見るところから始まる。吉田鋼太郎のハムレットは、「腕ずくの力でねじ伏せるような強さ」と「マグマの噴出」のようにほとばしる台詞が凄かった。エンデイングもオリヴィエのフイルムが使われ、ハムレットの遺体が担がれて城壁の丘の上へと運ばれていくシーンが映し出され、The Endのマークで舞台も終わる。しゃれた演出だった。今年一番の収穫といってもいいのは、ピーター・ブルックの「ハムレットの悲劇」。ところが「ロンドン通信」の鈴木真理さんの報告では、イギリスでの評価はあまり評判にもならず、次のように否定的である。
「小さな劇場で配役のダブリングも多く、フォーテインブラスも登場しないため、ハムレットの劇としてのスケールが非常に小さくなってしまっている。最初の宮廷シーンをハムレットと亡霊の出会いの後に置いたため、父暗殺の事実を知る前のハムレットのアンニュイが伝わってこない。To be speechをイングランド出立の時に移したのは問題である。云々」(引用は鈴木さんのメールより拝借)
「忽然として登場したホレイショーがあたりを不安げに見回す。舞台は一瞬の間、真空状態となる。そしてホレイショーは、その沈黙の重さに問いかける。「そこにいるのは誰だ?」。 <不安>は得体が知れない時に極限に達する。不安は亡霊の出現で、<恐怖>に変貌し、真空状態の均衡が崩れる。時間にして数分にも満たない瞬間、観客は息を呑む音さへ聞こえるような静寂の中で、舞台に釘付けになる。この瞬間に、もう舞台に電撃的にしびれてしまった。」というのが僕の感じた最初の感想であった。そして、僕にとってこの舞台は、ホレイショーの「そこにいるのは誰だ?」という台詞にすべてが収斂される。<アイデンテイテイ>の喪失と問いかけ、に。
このピーター・ブルックの「ハムレットの悲劇」を、びわ湖ホールで観られた「ユーリー」さんの「感想」が緻密で鋭く、実によく細部まで記憶されて記録しているのに驚嘆し、感歎した。(ユーリーさんのHP参考)
小さな試みではあるが、櫻会によるスタジオ公演「ハムレット」も印象に残る作品であった。
劇団扉座による「フォーテインブラス」と「ハムレット」の同時上演も興味深いものであった。特に印象的だったのは「ハムレット」のエンデイング。惨劇の場面に、舞台に立つフォーテインブラスに、赤ん坊を抱えた若い妻がそっと横に来て寄り添う。惨劇の後の明日への未来の約束と、柔らかな温もりを感じた。
最後は、蜷川幸雄の「ハムレット」。このことについては前号で触れたので特にあげないが、いろいろ批判、不満もあるが、蜷川幸雄の絶えざるチャレンジ精神を称えたい。蜷川はやはり「見せる」(=魅せる)演出家だと思う。
「ハムレット」関連では、劇団NLTの「くたばれハムレット」も面白く観ることが出来た。
今年は、「ハムレット」で何かと収穫の多い年であった。
01・12・2
|